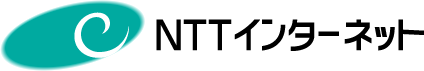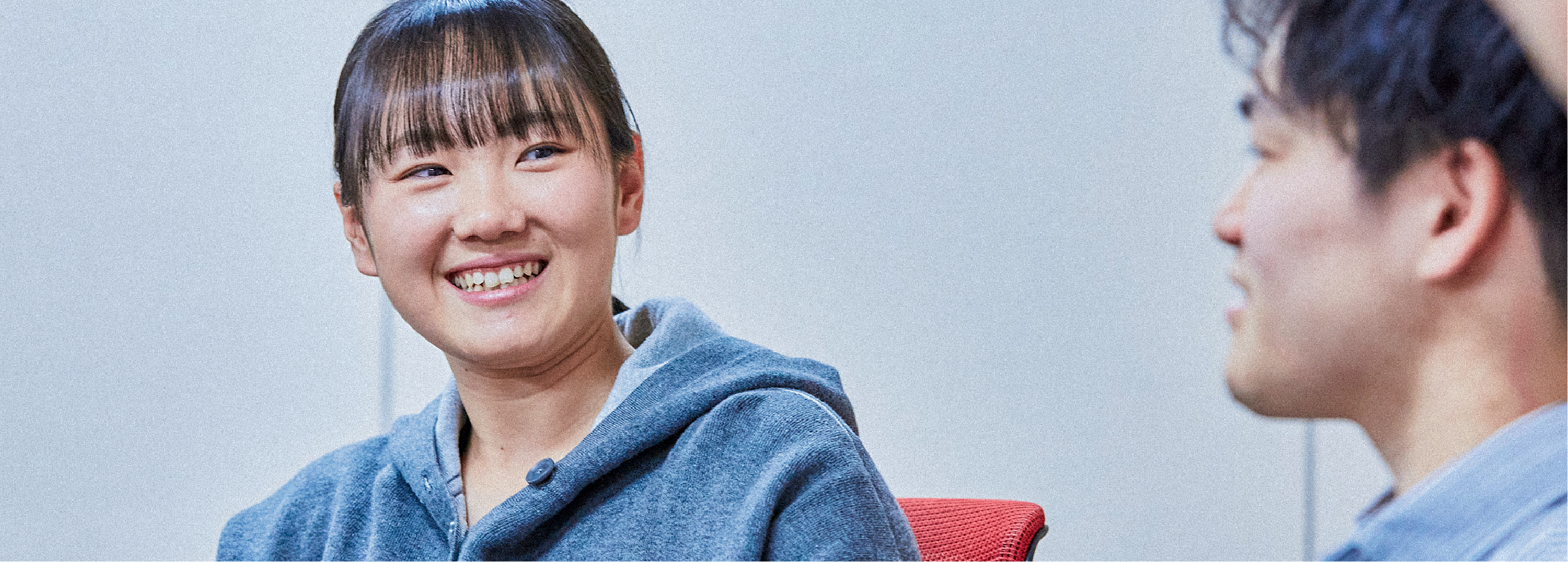Story 01
チームにおける担当業務・ポジション
- Y.J
- 当社として初めての研修に責任をもって取り組む
- アジャイル開発支援プロジェクトは少し特殊で、教育研修と現場への実装という2方向で複数のプロジェクトが並行して動いています。私が担当しているのは新入社員への3カ月間のアジャイル研修を実施する事務局です。最初に行った座学研修では外部講師の方のサポート。Webシステム開発の実践演習においては研修生たちのアジャイル開発に関する疑問や、クラウドやプログラミングなどの技術的な質問に答える役割を担っていました。新入社員へのアジャイル研修は当社として初めての試みであり、通常の開発案件とは異なるため戸惑うこともありましたが、責任をもって取り組みました。

- Y.N
- 25名の新入社員向けアジャイル研修を企画・運営
- アジャイル開発支援プロジェクトの一環として、新入社員25名を対象とした3カ月間のアジャイル研修のカリキュラム検討・実施・振り返りを担当しました。アジャイル開発とクラウドを活用したWebシステムを構築する実践的な研修です。3カ月にわたる研修のうち最初の1カ月は座学でアジャイル、クラウド、Webシステムの基礎を学び、次の2カ月でチーム毎に分かれてスプリント(一定の作業を完了するための短い工程)を実施。終了後の振り返りでは、今年度の総括を行い、次年度の研修について検討しました。私の役割は研修の運営と新人のサポートです。研修運営は初めての経験なので、大変なこともありましたが、とても良い経験をしました。

- S.S
- 変化に対応できる優れた柔軟性がチームの強み
- アジャイル開発を導入した、コミュニティの活性化を検証するシステムの開発にチームメンバーとして関わり、リリースまで遂行しました。アジャイル開発では「計画」「開発・テスト」「レビュー・フィードバック」を繰り返しながら目標の達成を目指します。計画からリリースまで一気通貫で業務に携わるため、メンバー全員が幅広い役割を担当することになります。それだけに、チームメンバーのコミュニケーションが活発で協力し合える雰囲気であることが重要です。このチームはとてもオープンで柔軟性があり、プロダクトの要件や優先順位が変わっても柔軟に対応できる、とても良い環境で開発に取り組めました

- Y.S
- スクラムマスターとしてスムーズな開発を支援
-
アジャイル開発の代表的な手法であるスクラムを採用し、スクラムマスターという立場でプロジェクトに参加しています。スクラムとは、開発チームが一丸となってスプリントと呼ばれる短い開発工程を繰り返す手法です。
スクラムの理論と実践について理解して、スクラムチームや組織が効果的に適用できるようにサポートすることが、スクラムマスターの役割です。開発チームとプロダクトオーナーの円滑なコミュニケーションを促進し、スクラムの価値観や原則を遵守することにより、スムーズな開発を行えるように支援しています。